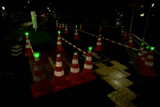買い物の帰り道だった。目的の店は近くて、わざわざ大通りに出るほどでもない。だから、なんとなく裏手の道を選んだ。日差しは強く、空気は乾いていて、冬の光みたいに影だけがくっきり地面に落ちていた。
角を曲がった瞬間、視界の奥に赤白のコーンがずらりと並んでいるのが見えた。工事の規制線が張られ、道路の縁が掘り返されて黒い土が露出している。転圧機の唸りと、ランマーの突き上げる音が、一定の間隔で胸を叩いた。作業員のヘルメットが陽を弾き、背後の駐車車両の窓も同じ光を返していた。
「ここ、まだやってるのか」
口に出した途端、喉の奥に乾いた砂が詰まったみたいに息が止まった。理由は分からない。ただ、この場所を“避けていた”記憶が、遅れて浮かんできた。思い出さないようにしていた記憶が、白い紙の裏から爪で引っ掻かれるように。
工事区画の向こうに、青い看板が見える。何度も目にしているはずなのに、その瞬間だけは「ここがどこか」を確かめるための標識みたいに見えた。現実に繋ぎとめる楔。そう思ったのに、次の拍でその楔がぐらついた。
歩道の端に、細い影が一本だけ増えていた。
自分の影とは別に、もう一本。形は人間の影に似ている。だけど、足がない。膝から下が途切れて、影の先端だけがコーンの列へ吸い込まれていく。日差しの向きは一定なのに、その影は陽光に従っていない。むしろ、こちらが影に引かれているみたいに、足元の感覚が一段重くなった。
振り返った。
何もいない。工事現場の奥に黄色いバケットが吊られたまま動かず、作業員が手元を見ているだけ。通行人もいない。なのに、背中の皮膚だけが、誰かの視線で薄く持ち上がっている。
規制テープが風に揺れた。赤と白の縞が、縫い糸みたいに震える。その震えが、転圧機の唸りとぴたりと重なった。
ドン。ドン。ドン。
一定の間隔で、地面が叩き固められていく。叩くたびに、掘り返された縁の黒さが、ほんの少しだけ盛り上がるように見えた。土が盛り上がるのではない。黒い“陰”そのものが、皮膚の下で膨らむみたいに。
そして、盛り上がった黒さの中に、瞬きのような動きがあった。
細い裂け目が開く。そこから覗いたのは、目ではなかった。目の“跡”だった。そこにあるはずの光が抜け落ちて、空洞だけがこちらを向いている。穴が、こちらを見ている。
あれがいる。昼間の工事の中に、確かに。
頭の中でそう断言した途端、足が勝手に規制線へ寄った。コーンの列が、通るべき場所を示しているようで、実際は“寄せる”ための柵に見えた。歩道の案内標識に描かれた人の絵が、矢印の方向ではなく、こちらを向いて立っている気がした。視線のないピクトグラムに、視線を感じる。ありえないのに、感じてしまう。
買い物袋の重みを確かめるように、手を握り直した。パンと牛乳と、夕飯の材料。日常の重さ。これでいい。これでいい、と自分に言い聞かせる。
ドン。ドン。ドン。
転圧機が一歩進むたび、掘り返された縁の黒い裂け目も、こちらへ一歩進む。距離が縮むのではない。こちらの“位置”が、工事区画の内側へ縫い直されていくような感覚だった。地面の線が、足の裏に合わせてずれていく。
背中が熱くなった。陽射しの熱ではない。背中に、何かがぴたりと重なる熱。ひとつ影が増えた理由が、分かった。
影は地面に落ちているんじゃない。背中に貼り付いている。
反射する車の窓に、自分が映った。顔色の悪い自分と、買い物袋を持った腕。その背後に、もう一人分の空白が重なっている。輪郭はあるのに、中身が透けている。透けているのではなく、“最初から何も写っていない”部分が、人体の形を保って立っていた。
恐怖は声にならなかった。声にした瞬間、日常が剥がれてしまいそうだった。だから、息を飲み込んだまま歩いた。規制線から離れ、コーンの列の外側を、できるだけ端を通って。
一歩、二歩、三歩。
数を数えた。数えれば、ここにいる自分を固定できる気がした。
四歩目のはずが、足裏が地面に触れなかった。
触れなかったのではない。触れたのに、感触が返ってこなかった。靴底が、空洞に滑り込むような、一瞬の無音。心臓が落ちる。落ちた先から、ドン、という転圧の音が遅れて響く。
慌てて足を引いた。何も起きていない。転んでもいない。周囲の誰も見ていない。なのに、背中の“貼り付いた熱”だけが、満足そうに少しだけ重くなった。
工事区画を抜けた。音が遠ざかる。日差しは変わらない。なのに、地面の影だけが変わらないまま、一本余分に付いてくる。足のない影が、コーンの列から離れて、こちらの歩道に移ってきた。
信号のない横断歩道を渡ったところで、ふっと、背中の熱が剥がれた。
代わりに、背中の一部が冷たくなった。服の布越しに、そこだけ“薄くなった”感じがする。皮膚が削れたのではなく、存在の厚みが削れたみたいに。
買い物を終えて帰宅し、袋からレシートを取り出した。いつもなら丸めて捨てる紙を、その日はなぜか捨てられなかった。紙の白さが気になった。まぶしいほど白い。
レシートの余白に、黒い指紋がついていた。
指紋ではなかった。小さな粒が規則正しく並び、指の腹で押し付けられた跡のように見える。アスファルトの骨材みたいな黒い粒。転圧機が叩き固めた粒。粒の並びは、点の列になっていた。
読めない。意味もない。なのに、その点の列を見ていると、背中の冷たい部分が、ゆっくりと“縫い直される”感覚がした。
その夜、眠りかけた耳に、遠くで工事音がした。
ドン。ドン。ドン。
もちろん、家の近くで工事なんてしていない。時計を見た。深夜だ。音は遠いのに、背中だけが近い。貼り付いた熱はもうない。代わりに、背中の冷たさが、じわりと広がっていく。
思い出したくない。忘れたふりを続けたい。
そう念じた瞬間、寝室の暗闇が一度だけ“縫い目”を見せた。部屋の角、クローゼットの扉と壁の間。閉じたはずの隙間が、呼吸をするみたいにわずかに開く。音はしない。開いたのは木戸じゃない。闇の厚みだけが、ゆっくり薄くなる。
以前、明け方にこの場所を通りがかった後に味わった恐怖が、息を吹き返した。
冬の明け方、赤と緑の規制灯がいっせいに瞬いていた。消えて、戻って、消えて、戻って――その繰り返しの“消えている側”にだけ、残っていたものがあった。赤でも緑でもないのに、消えないまま視界に居座っていた、小さな三つ。
今、その三つが、同じ並びでこちらを向いている気がした。
緑でも赤でもない。白でもない。色の名前がつけられないのに、光だと分かる。丸くもなく、点でもなく、湿った粒みたいに、こちらを測るように並んでいる。瞬きをしても消えない。目を閉じても、瞼の裏にその配置だけが残る。
ドン。ドン。ドン。
遠いはずの工事音が、床下から鳴っているみたいに近づいた。三つの光は揺れない。代わりに、隙間の縁が少しだけ“擦れる”。木と木が触れる音じゃない。ゴム底が何かを撫でたときの、あの嫌に生々しい擦過音に近い。
視線を逸らした。見なかったことにした。忘れたふりを、続けたかった。
それでも、光は薄れなかった。むしろ、隙間の暗さが“こちら側”へ滲むたび、三つはくっきりしていく。覗いているのは向こうではなく、こちらだと思った。入口を探しているのではなく、縫い目が解ける場所を確かめているだけだと。
壁の向こうで、糸を引く音がした。
引きちぎる音じゃない。きちんと縫い直す音だった。布が張っていく音。ほどけた部分が、見えない手で丁寧に寄せられていく音。
眠りに落ちる直前、三つの光が同時に瞬いた気がした。点滅ではない。合図でもない。ただ、数えられた、と分かる瞬きだった。
翌朝、クローゼットの扉は閉じていた。隙間も見えない。何も覗いていない。
だからこそ、背中の冷たさだけが残っていた。
思い出したくない。忘れたふりを続けたい。
そう思うたびに、目を閉じた暗闇の中で、赤でも緑でもない三つの位置だけが、正確に浮かび上がった。
この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。