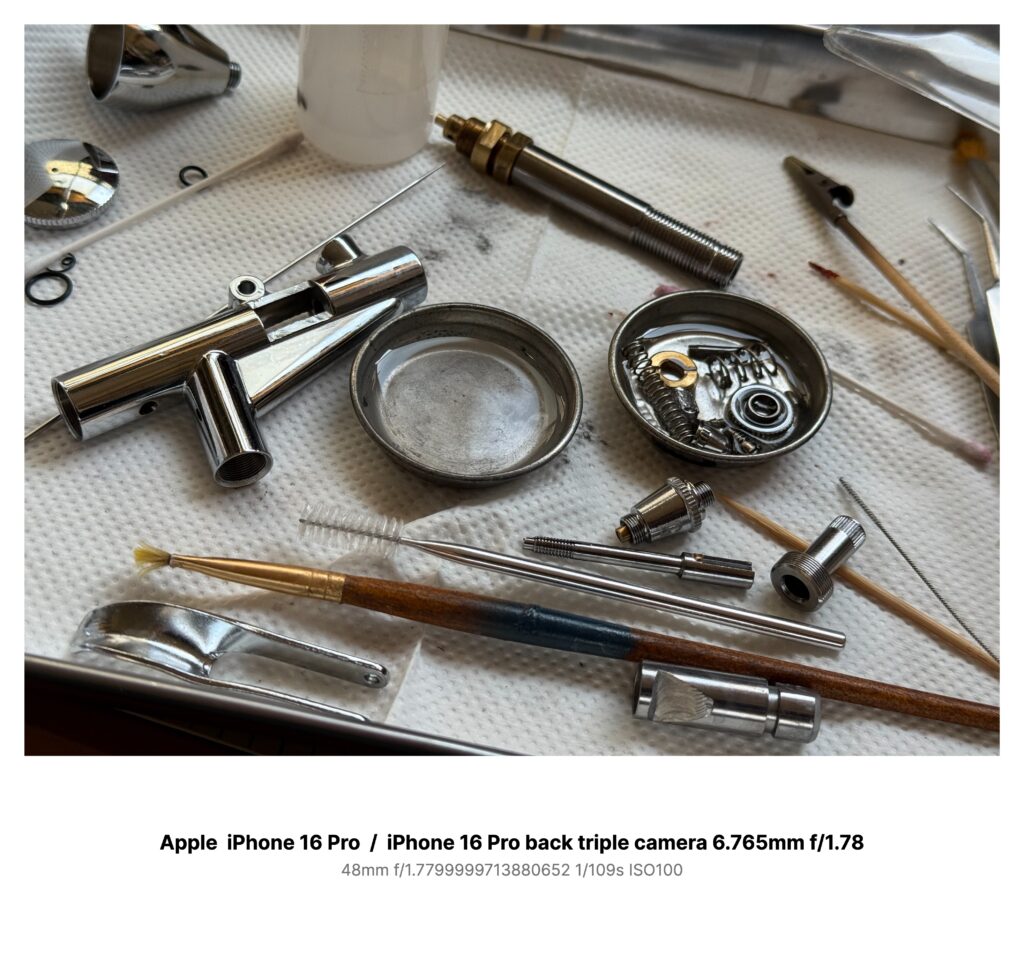エアブラシを分解するときは、必ずこの白いペーパータオルの上と決めている。
細い針やOリングを一つでも落としたら、その日の仕事は終わりだからだ。
銀色の本体、ニードル、ノズルキャップ。
ボトルキャップ代わりの皿には洗浄液を張り、もう一つの皿にはバネやワッシャーを沈める。
爪楊枝と綿棒、先の尖ったピンセット。
写真に写っているものは、だいたいいつもと同じ、はずだった。
違和に気づいたのは、ある遺影の修整をした夜だった。
「亡くなった父の、皺を少しだけ薄くしてほしいんです」
そんな依頼はこの仕事では珍しくない。
僕は古い写真の肌のざらつきを飛ばし、背景のゴミを消し、
影の境目をぼかす。
タブレットも使うが、最終的な質感は今でもエアブラシの仕事だ。
その晩も作業を終え、いつものように工具箱からトレイを取り出し、
エアブラシをばらして並べていった。
ふと、バネ皿の中に見慣れない部品が沈んでいるのに気づいた。
極細のコイルスプリング。
分解図のどこにも載っていないサイズだ。
「予備パーツでも混ざったか」
そう思って、捨てるのも気持ち悪いので、
空きフィルムケースに放り込んだ。
カラカラと乾いた音がした。
◇
余計な部品は、その後も増えていった。
別の依頼で、集合写真から「元夫」を消してほしいという相談があった。
肩と肩の隙間を埋めるために、僕は背景の木立を延長し、
袖のラインを描き足した。
エアブラシの噴きが少し不安定で、いつもより頻繁に分解洗浄をした。
そのたび、バネ皿の中に、分解図にない部品がひとつだけ増えている。
短いネジだったり、半月形のワッシャーだったり、
先端がわずかに曲がった不揃いな針だったり。
どれもステンレスのように鈍く光り、
指でつまむと、ほんの少しだけ温い。
部品の数と、最近「消した人」の数が、
なんとなく同じような気がしてきたのは三週間ほど経ってからだ。
◇
フィルムケースがいっぱいになった頃、好奇心に負けて、
僕は中身をペーパータオルの上にあけてみた。
チャラ、と音を立てて転がった金属片は、
不思議なことに、トレイの中央へ向かって自然と集まっていく。
傾いているわけでも、風が吹いているわけでもないのに、
どのパーツも、銀色の本体の近くへ吸い寄せられるように滑っていくのだ。
「静電気か……?」
自分に言い聞かせながら眺めていると、
バネが数本並び、その上にワッシャーが乗り、
細いネジが縦に差し込まれていった。
それは、人間の背骨のような形をしていた。
ペーパータオルの目地に沿って、
金属製の“脊椎”はゆっくりと伸び、
右の小皿の縁で折れ曲がる。
小皿の中では、小さなベアリングが二つ、
まるで眼球のようにこちらを向いていた。
僕は慌てて手で払った。
バラバラと部品が崩れ、
何事もなかったかのように散らばる。
ただ、小皿の底だけ、
洗浄液も入れていないのに、
水面のようにかすかに揺れていた。
◇
その夜、念のため記録用にと、分解した状態をスマホで撮影した。
あとで組み立てるとき、どこに何を置いていたか確認できるからだ。
─いまあなたが見ている、この写真だ。
翌日、別の遺影の依頼が入った。
今度は「病室の管を消してほしい」という、
少し重い修整だった。
腕から伸びる点滴のチューブや、
鼻にかかった細い管。
それらを、肌色と布の影で塗り隠していく。
塗っても塗っても、下から管のカタチが浮いてくるような気がして、
僕は何度もコンプレッサーを止め、
エアブラシを分解した。
乾燥した金属の匂いと、
薬品とインクが混ざったような甘い匂い。
爪楊枝の先には、赤茶色の塊が何度も絡みついた。
作業を終える頃には、
例のフィルムケースは二つ目に突入していた。
◇
深夜、静まり返ったアトリエで、
僕はまたトレイの上に部品を広げた。
銀色の本体、長いニードル、ノズル、キャップ、
ブラシ、綿棒、爪楊枝。
写真とほとんど同じ配置のはずだった。
ただひとつ違ったのは、
小皿の中だ。
バネと輪っかとネジが、最初から組み上がった状態で沈んでいる。
ベアリングが三つ、三角形を作るように並び、
その中心から、細いニードルが一本だけ立ち上がっていた。
ニードルの先には、透明な滴がひとつ。
床に落ちることもなく、
かすかに震えながら、そこに留まっている。
僕は息を止めた。
コンプレッサーは抜いてある。
風もない。
なのにペーパータオルの上で、
滴の影だけが、ゆっくりと膨らんだり、しぼんだりしている。
まるで誰かが、そこから呼吸しているみたいに。
「……やめろ」
思わず呟き、トレイごと持ち上げようとした瞬間、
空気が「シュー」と鳴った。
繋いでいないはずのエアブラシから、
白い霧が噴き出したのだ。
霧は一直線にペーパータオルに落ち、
そこに、人の腕の輪郭を描いた。
点滴の管が通っていたはずの場所だけ、
妙に濃く、立体的な影になっている。
霧が収まると、タオルには何も残っていなかった。
代わりに、小皿の中の金属が一斉に沈み、
底から泡のような音が一度だけ上がった。
◇
翌朝、印刷所から電話があった。
昨夜仕上げて送った遺影について、
「管を消してくれてありがとう。ただ……こんなお願いはしていないのですが」
という伝言付きのメールを転送された。
添付されていた完成品のスキャンには、
微笑む老人の肩に、誰かの手が添えられていた。
手首から先だけの、青白い手だ。
原稿のどこにも、そんなものは写っていなかったはずだ。
驚いて自分のデータを開くと、
僕の保存していたファイルにも、同じ手があった。
ただし、老人の顔の皺は、依頼よりも徹底的に消えている。
肌が不自然に滑らかで、
陶器のように光っていた。
それからというもの、
エアブラシを使って「何か」を消すたびに、
写真のどこかに、消したはずの形が戻ってくる。
背後の窓ガラスに映った輪郭や、
テーブルの木目に紛れ込んだ指の跡として。
そして分解のたび、トレイの上には、
分解図にない部品がひとつずつ増えていく。
最近では、フィルムケースが四つ目になった。
中身をあける勇気は、もうない。
ただ、たまに蓋の隙間から、
コンプレッサーを回していないのに聞こえる、
「シュー……シュー……」という微かな音だけが、
机の上で呼吸を続けている。
この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。
(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –