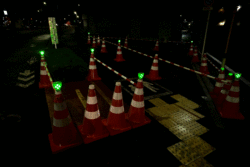以下の怪談で使用した写真は、加工前のものをストックフォトサービス「PIXTA」で販売しています(定額会員の方は定額枚数の範疇で無料ダウンロード可能です)。

TRUNK-STUDIOさん(No.2641798)のプロフィール - PIXTA
TRUNK-STUDIOさん(No.2641798)のプロフィール。写真素材・イラスト販売のPIXTA(ピクスタ)では11,550万点以上の高品質・低価格のロイヤリティフリー画像素材が550円から購入可能です。毎週更新の無料素材も配布しています。
一部の写真は、その他のストックフォトサービスでも販売しています。
shutterstock
https://www.shutterstock.com/ja/g/trunkstudio
photoAC
https://www.photo-ac.com/profile/26455964
imagemart
https://imagemart.jp/ja/@TRUNK
写真の追加リクエストや、掲載内容のお問い合わせは、各ストックフォトサービスからお願い致します。