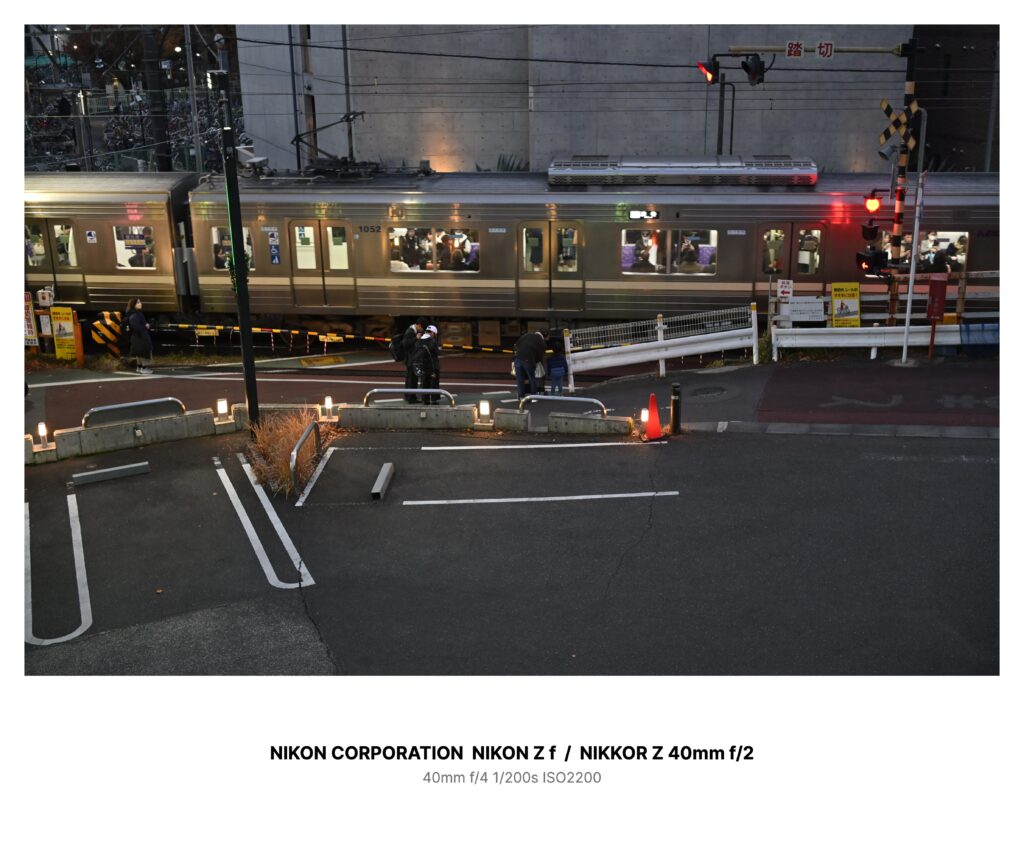その踏切は、昔から「どこにもつながらない踏切」と呼ばれていた。
写真を見ればわかるように、電車の向こう側には道路がないように見える。線路を挟んで道が途中で切れ、赤い警報灯だけが宙に浮かんでいるみたいに。
けれど実際には、道路は線路に対して斜めに走っていて、通過する電車の車体に隠れてしまっているだけだ。
それを知っている地元の人間からすれば、ただの撮影角度の問題にすぎない。
それでも、子どものあいだでは別の説明が広まっていた。
――踏切の先は、「子どもだけの駅」につながっているんだって。
――電車の窓に押しつけられてる顔、あれ全部、そこから乗ってきた子なんだよ。
危ないからと、親たちが踏切で遊ぶことをきつく叱るうちに、そんな物語が生まれたのだろうと、大人になった今では思う。
◇
数年ぶりに帰省した晩、私はその踏切の上にある小さな立体駐車場の二階から、ぼんやりと下を眺めていた。
冬の夕方、まだ空は完全には暗くなく、街灯と電車の室内灯がせめぎ合う時間帯だ。会社帰りの人がぎゅうぎゅうに詰まった車両が、警報音を残して通り過ぎていく。
遮断機の手前では、何組かの親子連れが足を止めていた。
ベビーカーを押している母親、手をつないだ父親と幼い男の子。写真にも写っている、あの親子だ。
そのとき、ふいに昔の出来事を思い出した。
小学校の同級生に、鉄道が好きな男の子がいた。
いつも電車の形式番号を暗記していて、下校時間になるとランドセルを家に放り込んで、この踏切まで走ってくる。
父親と一緒に列車を眺めるのが日課で、二人並んで線路を見つめている後ろ姿は、近所の名物みたいになっていた。
ある冬の日、その子の父親は、なぜか一人で踏切に立っていた。
子どもの姿はなかった。
不思議に思っているうちに、帰りのラッシュの電車がやってきて、踏切の周りは警報音に包まれた。
電車が通り過ぎる一瞬、私は線路から少し離れた歩道にいた。
走り抜けていく銀色の車体、その連なった窓ガラスに、奇妙なものを見た。
窓という窓に、子どもの顔が押しつけられていた。
曇りガラスに額をくっつけて中を覗くみたいに、十も二十も、同じくらいの年格好の子どもたちが、ぺたりと貼りついてこちらを見ている。
その後ろに、大人の乗客の影が、まるで背景の模様のように薄く揺れていた。
私は目の錯覚だと思った。
スピードのせいで、いくつかの顔が連続して重なって見えただけだろう、と。
ところが、父親のほうは違ったらしい。
電車が通り過ぎたあと、彼は遮断機をにらみつけたまま、かすれた声でこう言った。
「……あいつ、あそこにいた」
それからしばらくして、その家には警察が出入りするようになった。
子どもが突然いなくなったのだと、近所の噂で聞いた。
誘拐の線も疑われたが、結局手がかりは見つからず、あの父親はやせ細って、町から姿を消した。
◇
駐車場の手すりにもたれながら、私は下の景色を眺め続けた。
あの頃と違って、踏切の周辺は整備され、歩道には小さなライトが並んでいる。
車止めのコンクリートブロックの向こうには、白線だけが引かれた空の駐車スペース。
警報機が鳴りだした。
線路脇の親子が、自然と足を止める。
男の子は、父親の手からするりと抜けて、遮断機のぎりぎりまで駆け寄った。
私は思わず身を乗り出した。
それでも、父親はすぐに追いつき、背中を押さえて止めた。
男の子は不満げに振り向き、何かを訴えるように父親に話しかけている。
その視線の先を追って、私はようやく気づいた。
彼が見ているのは、電車そのものではない。
もうすぐ入ってくるはずの車両の方向ではなく、踏切の先――電車に隠れて見えなくなる、あの斜めの道路の向こう側を、じっと見つめているのだ。
やがて、ホームを出た電車のライトが遠くに光った。
金属のきしむ音が近づいてくる。
私は反射的に、車体の窓ガラスを凝視した。
電車が踏切に差しかかった瞬間、私の視界は淡い光で縫いとめられた。
窓という窓に、やはり顔が並んでいた。
今度は、はっきりと「子どもだ」とわかる顔だった。
髪の長さも、表情も、服の色も、みんなばらばらなのに、どの顔も、同じ方向を向いている。
踏切の手前ではなく、その少し先――写真では空白に見える、電車の向こうの斜めの道路のあたりを。
顔のいくつかは、窓ガラスに頬を押しつけたまま、口だけを動かしていた。
私には何を言っているのかわからない。
ただ、その動きが妙にゆっくりで、音のない呼吸のように見えた。
電車の騒音に紛れて、男の子の声だけがかろうじて聞こえた。
「……あっち、行きたい」
父親の手が、びくりと震えた。
次の瞬間、車体が完全に踏切をふさぎ、親子の姿は見えなくなった。
私の耳には、警報音とレールを滑る金属音しか届かない。
電車が通り抜けていく間、私は目を閉じなかった。
窓の中の子どもたちは、ずっと同じ場所を見ていた。
やがて最後尾車両が過ぎ、がこん、と線路の継ぎ目の音が遠ざかる。
踏切の遮断機が上がり、赤いランプが消えた。
親子は、まだそこにいた。
男の子は、さっきと同じように遮断機のそばに立っていたが、今は父親の手を握りしめている。
その顔つきが、どこか違って見えた。
さっきまで、列車を待ちきれないような落ち着きのなさがあったのに、今は妙におとなしく、遠くの何かを観察するような目をしている。
父親はしゃがみ込み、何度も男の子の名前を呼んでいた。
呼びかけられるたびに、子どもは一拍おいてから返事をする。
まるで、自分に向けられた名前が、少しだけ他人のものに感じられているかのように。
やがて二人は、斜めの道路を駅とは反対側へ歩いていった。
男の子は一度だけ振り返り、線路の向こうを見つめた。
その視線を追うようにして、私は空っぽの駐車スペースを見下ろす。
アスファルトの色の濃淡、白線、車止め、倒れたままのコンクリート片。
何も変わっていないはずだった。
ただ、その一角だけ、ほんのわずかに濃く影がたまっているように見えた。
そこに、電車の窓からこちらを見ていた子どもたちが、列を作って静かに立っている光景が、頭から離れなかった。
あの踏切を通る親子は、必ず子どもを前に立たせる。
危ないはずなのに、なぜかみんな、そう並ぶ。
そして電車が通り過ぎたあと、時々、子どもの表情や仕草が「少しだけ違う」と感じることがある――そう語る人は少なくない。
踏切の向こうの道路は、本当はちゃんと続いている。
けれどあの夕方、走り去る電車の窓に並んだ顔を見てしまってから、私はもう、完全に信じ切ることができなくなっている。
あの線路の向こうには、地図には載らない、子どもだけの駅があるのではないか。
電車の車内で窓に張りついている子たちは、そこで乗り込んできて、外にいる誰かと席を交換する順番を待っているのではないか――そんな考えが、冗談では済まされないほど、はっきりと形を持ってしまったからだ。
この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。